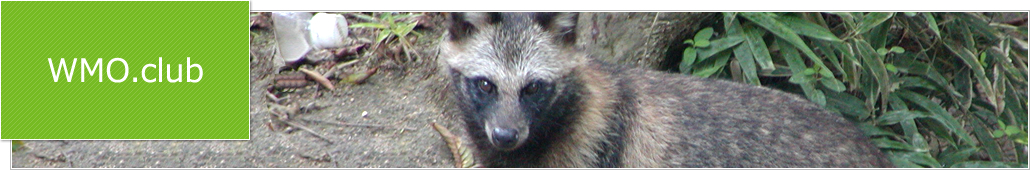No.100WMOのあゆみ
WMOのあゆみ
WMO代表 羽澄 俊裕
おかげさまで、私どもの機関誌「フィールドノート」が100号を迎えることになりました。25年という長きにわたり支えてくださった読者の皆様には、心から御礼申し上げます。この間、日本の社会情勢もずいぶんと様変わりして、野生動物の保護のありようについても大きく異なってまいりました。私どもWMOもそうした時代の変化に柔軟に対応してきましたが、そのときどきに何を思い、ここまで歩んできたのか、反省をふまえつつ振り返り、新たな出発の機会としたいと思います。
はじまり
いまから25年前、私と初代代表の東英生の二人は、環境庁(現環境省)の事業で、栃木県の男体山麓にある営林署の小屋にこもり、夜明けとともに雪を踏みしめながらシカの生け捕りトラップを見回り、捕まったシカを麻酔で眠らせては手作りの発信機を装着する。そんな仕事を続けていました。20日ほど山にこもって東京に1週間ほど戻り、また山にあがるという暮らしをしていましたから、まさに寝食を共にし、同じ釜の飯を食って、夢を語り合うという貴重な時間でした。
当時は高度経済成長のさなかで、森林は盛んに伐採され、世間の関心が白神のブナ林に向いているときでさえ、東北の各地でブナの木を満載したトラックが奥山の林道を走りぬけていました。奥山が裸になればクマが里に出るのは当たり前です。異常出没と騒がれクマが駆除されるたびに、このままでは絶滅してしまうと強い危機感を持ちました。また、東英生のほうも、無造作に駆除がすすむサルの被害問題に直面し、また、1970年代のカモシカ裁判以降、特別天然記念物でありながら駆除されるカモシカを研究機関へと運びながら、この現状を少しでも良くしたいと強い思いを持っていました。
20代半ばの男が2人、薪ストーブに火をつけ、ランプの灯りの下で寝ても覚めても野生動物のことを語りながら、既存の組織にはできないことをやる。野生動物の保護を本気でやる。そういう組織を作ろう。そういう思いの中からWMOが生まれました。
名前の由来
私たちの目的は、野生動物の保護をきちんとこなす社会システムを作ることでした。当時の自然保護は学生運動時代の流れの中にありましたから、対行政の反対運動をするのが主流でした。自然は公的なものであり、それを護ることは公的機関の責任である。個人が手弁当でやるのは筋が違う。そういう思いの一方で、行政側に専門スタッフもいないのに、そもそも、きちんとやれと要求することには無理があると感じていました。
ですから、私たちの描いたイメージは、将来において行政組織にワイルドライフ・マネジメントの体制を定着させること。それを最大の目標として、そのためのサポートをする組織を作ることでした。その結果、「野生動物保護管理事務所」という、長くて、面倒で、ときに公的機関であるかのような誤解を生む名前が生まれることになりました。
当時はまだ、ワイルドライフ・マネジメントが浸透しておらず、自然保護関係者の間では、「自然を管理する」ことへの抵抗感が強くありました。そういう時代の中で、ワイルドライフ・マネジメントという英語に対して「野生動物保護管理」という訳語が生まれたわけですが、そもそもの意味をきちんと理解するならば、こんなまどろっこしい造語をすることもなく、「管理」の一語でよかったはずのものです。そんな思いを持ちつつも、ワイルドライフ・マネジメントをやっていくのだという創設時の意思を忘れないように、この言葉を社名に入れました。また、よくあるように、研究所とか、研究センターといった名前にせず、事務所としたのも、マネジメントの本質は研究ではなく調整にあると理解して、自分たちの立ち位置をよく見定めて決めたことです。
バブル時代
1983年に旗揚げしたことは後で思えば幸運だったかもしれません。まさに日本はバブル経済の時代に入り、どこでも金余り現象がおき、世の中のすべてが「ええじゃないか」の馬鹿踊りをしていた時代でした。若造が野生動物の会社を作っても日常生活に困る時代ではありません。
私たちの理想は行政から委託を受けて仕事をすることでしたが、当時は行政の動物調査に予算のつく時代ではありませんから、大学や試験研究機関にいる研究者の調査のお手伝いをさせていただくことから始めました。片方で、バブルの勢いにのって森林を売り払ってゴルフ場にするといった、開発にともなったアセスメント調査が盛んにおこなわれた時代でしたから、そうした調査に参加していれば、とりあえず若造が飯を食うには困りません。そこで軍資金を稼いでは山に行き、好きなだけ動物の調査をする。それですべてが忙しく回っていました。
動物調査用の発信機を手作りして研究者に提供するとか、困難な捕獲を肩代わりしたり、捕獲された動物や血液サンプルなどを大学に運んだり、解剖のサポートをしたりすること。とにかく動物の調査に関することで、相手が意欲ある研究者ならばなんでも手伝いますという姿勢で各地を飛び回っていました。徹夜で発信機を作っては翌朝一番で捕獲の現場にかけつけるとか、秋田や下北半島の先まで東京から一気に車を運転してかけつけるなんてことは日常茶飯事でした。とはいえ、時間を惜しむように現場に出ることは、その後の私たちの大きな財産になっていきます。それが勉強であり、自分たちの理想を外にむけて発信する機会であり、仕事でした。
法人化
バブル時代の幕引きは戦争の記憶を伴う昭和の終焉とともにやってきました。元号が平成に変わり、1990年代は、日本の経済が冷え込んで勢いを失います。その頃には、私たちにも行政から仕事をいただく機会が少しずつ増え始めていました。そんな中で、ある役所の担当から、法人でないと仕事を出しにくいというアドバイスをもらいます。まだ、NPO法人制度のなかった時代のことです。どこかでバブルのあぶくをすくって財団法人にできないかと夢ばかり追いかけていました。ずいぶんと迷いましたが、名前がどうであれ、やっている仕事の内容で評価してもらえばよいという姿勢で腹を固め、ちょうど商法改正の直後ということもあって、1991年に株式法人として再出発することにしました。そして、法人化とともにWMOも世間並の組織体へとしだいに移行していくことになります。
その時点でNPO法人制度があれば、迷わず選んでいたと思いますが、今、振り返れば、これでよかったという思いでいます。現状を見ますと、NPO法人であれ、株式法人であれ、しょせん組織の運営と職員の給与以上に利益を生み出すことのできるような職業分野ではありません。また、自然保護などボランティアに無償奉仕でやらせておけという風潮の強いこの国で、我々はこれで飯を食っているのだという意思表示をする意味でも、けして悪くなかったと思っています。
小泉改革以来、公的業務のアウトソーシングで、なんでも民活の風潮が生まれていますが、それも確固たるものともいえず、社会や政治の動向でどうなるものやらわかりません。しかし、自然環境に関することは厳然たる公的業務だと思います。監督責任は行政にある。核は官にあって民がサポートする。そういう構造が当然のことです。まったく不透明な時代ですが、先々何が起ころうとも、WMOの本来の目的を達成するために、目の前の不安にしばられることもなく、柔軟に歩を進める。そんなしなやかさを持ち合わせていたいものだと思います。
環境の時代の中で
話は少しさかのぼりますが、1990年代に日本経済が低迷していく一方で、野生動物については追い風が吹き始めます。1992年にブラジルのリオデジャネイロで地球環境サミットが開かれ、環境の時代が幕をあけました。そこで生物多様性条約が生まれ、後に日本も加盟します。この条約は、いってみれば野生生物保護の世界憲法のようなものです。加盟国は生物多様性国家戦略の作成が義務付けられています。
そして国内では、1999年に鳥獣保護法に特定鳥獣保護管理計画制度が盛り込まれました。この制度は、昭和時代に林業試験場を中心に展開されていたネズミやノウサギといった害獣管理以来、はじめて生物種の保全を前提にしてワイルドライフ・マネジメントの思考を取り込んだ制度といえます。私たちWMOも、この制度が正しく現場で活用されるよう、最大限のサポートをしてきましたが、なかなか問題は解決しません。
一方、野生動物の生息状況は大きく変化しています。大きな原因は戦後の高度経済成長とともに労働力が都会にシフトし、農山村の過疎がどんどん進行してきたことにあるといえるでしょう。農林業の力が衰え、地域の生活の一部としての山林の手入れや野生動物への対応力が失われ、野生動物を押しとどめることができなくなったというのが実情でしょう。その結果、野生動物の生息分布は大幅に回復し、たとえばシカやイノシシの分布が北上しています。農地の裏では大型の獣が普通に生息するようになりました。こうして、以前にもまして獣害は大きな社会問題となっています。こうした事態に対処すべく、強い要請のもと、2008年春に農水省所管の「有害鳥獣被害防止特措法」が生まれました。
この法律は地域社会が協働して事にあたり被害を防除することや、先にあげた鳥獣保護法の特定計画にリンクさせて野生動物の保護管理を担保する仕組みになっています。しかし、現実には、「害獣は駆除する」という地元の強い習慣のような思考から、なかなか話はうまく進みません。しかし、過疎とともに猟師がいなくなる時代を迎え、このままではまもなく駆除は機能停止に陥ります。捕獲はもちろん重要なオプションですが、駆除ばかりにたよらず、そもそも被害を未然に防ぐ社会体制を作る。そこに力をそそいでいかなければなりません。
また、2005年には生物多様性条約の中で重視される課題に応えるべく、外来生物法が作られました。私たちのところにも、外来動物の調査や除去に関する相談が増えました。可愛いという理由で持ち込まれた動物が逃げ出し、野生化し、日本の野生動物のニッチを奪い、日本の生物を食べるなどの生態系への害や、遺伝子の交雑問題まで生まれています。 このように、次々に法律が生まれているにもかかわらず問題はなかなか解決しません。その理由をつきつめてみると、やはり現場でうまくいくための仕組みが生みだされていないことが一番の理由であると強く感じます。
私たちがそれぞれの事業を通してあくせく走り続けていても、それが場当たり的な対処であるうちは、根本の解決にはつながりません。やはり、現場から国家まで一貫した体系的なワイルドライフ・マネジメントの仕組みがあって、しっかりとした全体計画と、それを遂行する体制が必要です。そうでなければものごとは空回りするばかりで、予算の無駄遣いにもつながります。
これから
最近の社員が生まれる前からWMOの看板をあげていたという現実があるにもかかわらず、残念ながら、日本のワイルドライフ・マネジメントはまだまだ未完成です。社会が変わるということは時間のかかることです。この時代、世間では社会不安が広がり、深く浸透しているように感じます。世の中のゆとりのなさは、戦争とならんで自然保護の最大の敵といえるでしょう。経済的ゆとりと心のゆとりが同じであるか否かは議論の必要なところですが、大事なことを見失うことなく、地に足をつけてしっかりと歩いていきたいものです。とはいえ、現在の混沌とした状況は、長く日の目を見なかった分野には新たな転換の機会でもあります。野生動物の保護を推進する社会の仕組みを作り上げるには、絶好の機会の訪れと考えたいところです。
大学では、野外における生物や生態系に関する基礎研究が盛んに行われ、そこから専門性ある人々がたくさん輩出され、世の中の要所に配属される。地方の博物館は自然を志向する学生を受け入れ、地域の自然環境に関する野外研究の核として機能する。また、ワイルドライフ・マネジメントの核となる機関が地元の野生動物とそれをとりまく自然環境に関する監視モニタリングを続けている。行政は、そこから生まれる膨大な情報に基づき、計画を練り、社会的な合意形成をおこないつつ自然環境や生物多様性の保全を実行に移していく。さらには、リスク・マネジメントの観点から、柔軟に計画の修正をかけ、自然環境との共生を模索していく。そんな仕組みを作りたいものです。
そして、一連の仕組みを支えていくには、その機能の全体像の見える人が、あちこちにいることが理想です。自然についての哲学や思想は人それぞれでよいのですが、自然を残すための仕組みの上では、合意形成に参加していくという責任を自覚している。そういう人がたくさん生まれてくることが大事です。
21世紀は「生態系で考える」を考える時代になります。そしてエコシステム・マネジメントという新たな仕組みを確立するという、気の遠くなるような作業にチャレンジしていくことになるでしょう。これからの時代に、WMOは何をしていくべきか。もっと深く広く思考し、さらに山を歩き、きめ細かく現場に貢献する組織として、模索を続けていきたいと思います。また、みなさんに期待される組織であるよう、さらに努力してまいります。
| No.100 | 一覧に戻る | No.99 |