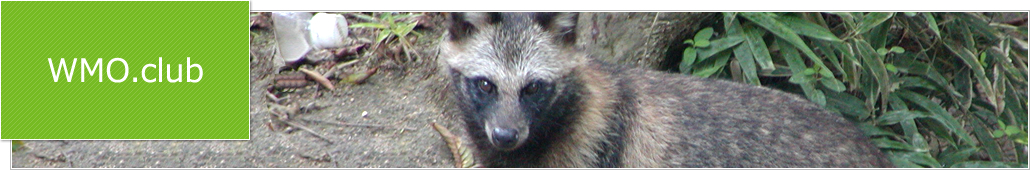No.132 シカ肉とわたし
シカ肉とわたし
田中 啓太(WMO)
私が初めて(意識して)シカ肉を食べたのは高校生のときでした。カヌーイストで作家、自然保護活動家でもある野田 知佑さんという方をご存じの方もいらっしゃるかも知れませんが、その野田さんの一味に藤門 弘という男がいまして、両親の大学時代からの友人ということで昔から親交があり、そのときも藤門からの突然の電話でことが始まりました。
「ケイタ、良いシカ肉が手に入ったから野田さんと一緒に食おうぜ」
今考えると色々と不可解なことが多いのですが、中野あたりだったと思いますが、マンションの1室を藤門と共に訪れました。そこには野田さんの他にも先客が何人かおり(記憶が正しければ彼らの一味で、作家の夢枕 獏さんもいた気がします)、銀座だか西麻布だかのオシャレなイタリアンレストランでシェフをしている方が調理したという、エゾジカのカルパッチョをいただきました。添えてあるルッコラとともに、上からオリーブオイルをさっとかけただけの、カルパッチョにしては少し厚みのある大きな切り身のシカ肉に、大きく削ったパルミジャーノ・レッジャーノの”板“が無造作にかぶせてあるという、今にして思えばかなりワイルドなカルパッチョでした。高校生の私にとっては初のシカ肉だっただけでなく、カルパッチョも初体験、そもそもヨーロッパでも生で肉を食べる習慣があることすら知りませんでした。そんなせっかくの貴重な初体験だったのですが、若さゆえに目の前の肉塊にがっついてしまい、瞬く間にカルパッチョを平らげてしまいました。そのため、すごく感動したという記憶はありません。とはいえ、成長期で底なし胃袋だった私でも食いでがあるほどのしっかりした肉であったにもかかわらず、衝撃的なおいしさだったことははっきりと憶えています。その後はあまり面白くない大人の話に交じっていたわけですが、話の内容はあまり覚えていないものの、四万十川の郷土料理で、日本酒に川エビやカニを漬けたという、珍しい酒があったのを覚えています。ただ、飲んだかどうかはみなさんのご想像にお任せします。はじけたばかりだったバブルの、浮かれた気分がまだ色濃く残っていた時代でした。
東京に住んでいると、シカ肉が容易に手に入ることはありません。その後は満足行くまでシカ肉を食べられたことはほとんどないのですが、そんなシカ肉日照りの人生が一変する転機が訪れたのは、調査のためにニューカレドニアに行くようになったときでした。ニューカレドニアは、グレートバリアリーフ(オーストラリアの北東部沿岸)の真東かつニュージーランドの真北にあり、珊瑚海と南太平洋を隔てるように位置している、面積は四国ほどの細長い島です。ジェームズ・クックによって“発見”され、山がちな地形がクックのルーツであったスコットランドを彷彿とさせるということで、ニュー・カレドニア(カレドニアはラテン語でスコットランド)と名付けられました。現在はフランスの海外領土となっており、公用語はフランス語、通貨はパシフィック・フランが用いられています。ちなみにフランス語ではNouvelle-Cal?donie(ヌヴェル・キャレド二)といい、私はこのフランス語名の方が好きです。一方、もともと住んでいたメラネシア・ポリネシア系住民の間では、Kanaky(カナキー)と呼ばれることもあります。
さて、なぜそんな場所でシカ肉かというと、アカシカのハンティングが盛んだからです。もちろんアカシカがニューカレドニアに自然に分布しているはずはなく、もとは「植民地でもシカ狩りがしたい」というヨーロッパ人入植者たちの誠に身勝手な動機で持ち込まれました。そして自然に繁殖するようになり、しまいには植物については単位面積あたりの固有種数が世界一という、この世界でも有数の生物多様性ホットスポット(図1)を、アカシカたちは跋扈するようになったのです。もちろん、生態系の保全や固有種・希少種・絶滅危惧種の保護は政策的にも重要度は高いのですが、それでもハンティング人気は根強く、近年では入植者の子孫だけでなくメラネシア・ポリネシア系住民にも浸透してきており、シカの駆除・根絶という方向にはなかなか政策が進んでいかないようです。

そんなわけで、シカ肉はいくらでも食べられる環境に身を置いたわけです。ただ、最初のシーズンは右も左もわからなかったうえ、資金も潤沢ではなかったので、レストランに行くような時間的・経済的余裕はありませんでした。しかし、2シーズン目に入ると余裕もでてきて、外食をする機会も増えました。2シーズン目の滞在が始まったばかりのころ、宿舎などでお世話になっている現地の方や、ニュージーランドの大学から研究にきている研究者たちと、地元のレストランに行きました。その時はまだシカ肉を食べていなかったので、シカか、もしくは何かジビエを食べたいと思っていた私は、幸いにも英語が通じる若いウェイターにジビエが食べたい旨を伝えました。ところが、そのウェイターのお兄さんは完全に「はてな?」になってしまったのです。
「それ(ジビエ)って何?」
ええ~!?!?フランス人で、しかもこんなところに住んでいるのにジビエを知らないの~!?
困った私が、local foodだのdeerだのrabbitだのpheasantだの、思いつく限りのジビエを連想できそうな単語を挙げていると、それまでは食前の会話を楽しんでいた同行者たちも私とウェイターのやり取りが気になってしまったようで、一体こいつは何のことを言ってるんだ、と大騒ぎになってしまいました。そしてとうとうその瞬間がやってきました。ウェイターの兄ちゃんは
「ああ~!わかった!gibierか!」
あえてはっきり発音したウェイターの兄ちゃんの「ジビエ」は「ジビエ」ではなく、聞こえてきた音は「シュビエ」に近いものでした。彼がわからなかったのは私の発音だったというわけです。そうそう、フランス語には「ヂ」の音がないので、「ジ」の音を出すときは決して舌を歯にくっつけてはならない、と大学の第二外国語で習ったのを思い出しました。日本語も英語も「ヂ」と「ジ」は区別していないけれど、フランス語の発音は次元が違っていたのです。
人間、発音を間違えると不思議とついこっ恥ずかしく感じてしまうもので、先程自分の口から出た「ジビエ」の音が途端にどうしようもなく野暮ったく感じられ、恥ずかしさのあまり顔や耳が真っ赤になったのを感じました。ただ、この体験のおかげでフランス語の発音を“心で”学ぶことができ、その後は発音だけは褒められるようになりました。例えばハム・ソーセージ類はjambonで、シカ肉のサラミなどはjambon de serf(ジャンボン・ドゥ・セール)となりますが、ジャンボンの「ジャ」はやはり「シャ」と「ジャ」の中間のような音になります。フランス語の発音で注意が必要なのは、咽頭を震わせるrや、鼻母音だけではなかったのです。
しかし、そんな思いまでして注文したシカ肉のステーキは品切れで、さらにウサギも品切れ、残念ながらその夜はジビエを食べられず、牛肉で我慢せざるを得ませんでした。シカ肉など腐るほどあると聞いていたので、どうにも腑に落ちなかったのですが、しかたありません。さらに、その後もしばらくはシカ肉のお預けはつづきました。スーパーで売っていないのです。皮をはいだだけのウサギや、豚の顔なども売っているというのに。その後滞在が長くなるにつれてだんだん察してきた理由は単純なものでした。シカ肉はあくまでも自分で狩るか誰かにもらうものであり、お金を出して買う人などいないのです。レストランで品切れだったのも、たまたま不猟続きだったか、もしくは入手するのが面倒だったか、おそらくそういったどうでも良い理由でしょう。結局、シカ肉との再会は無感動にやってきました。ご多分に漏れず我々が借りている宿舎(家主の離れ)でも、冷蔵庫の冷凍室には無造作にビニール袋に入れられた、いつから入っているかわからないシカ肉がごろごろ転がっていました。久々に食べたシカ肉は、確かにおいしかったのですが、しっかり味付けをしたにもかかわらずほんのりと冷蔵庫の香りがしました。
我々が調査のベースにしていたのは島の中部にあるファリノ(Farino)という、人口300人ほどの小さな市でした。ただ、人口300人とはいえ農産物には定評があるようで、国際空港で売っているニューカレドニアの看板商品の中で、最も単価の高い高級コーヒーはファリノ産、他にもオレンジなどが特産ということで、経済的には潤っているようでした。月に1~2度、市庁舎の前でmarch?(青空マーケット)が開催され、住民の方たちが作った野菜や蜂蜜、キイチゴジャムなどなどなど、つい「これ無しでは生きていけない」と思ってしまうほどの、おいしい食べ物が山ほど売られており、生のままでは金銭的価値の無かったシカ肉もここでは様々なタイプの特製jambonに姿を変え、商品として並んでいます(図2)。中でも私が一番好きだったのは香草ベーコンでした。タイムやローズマリーなど、ごく一般的なハーブ類をミックスしたものをherbes de Provence(エルブ・ドゥ・プロヴァンス)というのですが、日本でいえば醤油なみに高頻度で使用されているようで、スーパーでも特大サイズで売っています。そのハーブをふんだんにまぶして作られたベーコンは、ぎゅっと濃縮されたシカ肉の風味と独特の甘みがハーブの爽やかな香りとともにじっくり熟成されて、絶妙なハーモニーを醸し出しており、病みつきになるおいしさでした。おそらく燻製にはしておらず、調理法としてはジャーキーのように乾燥させただけと思われます。塩分もあまり強くなく、香草の殺菌力と乾燥だけで腐敗を防いでいるのでしょう。もし自家製のベーコンなどを作る方がいらしたら、一度お試しになっても良いかも知れません。

ニューカレドニアの生物問題はヨーロッパ列強による植民地支配の歴史だけでなく、近年のグローバル経済や技術革新の影響も絡んでいて、非常に複雑です。有史以前にはオオコウモリ以外の哺乳類は存在しなかったとされていますが、現在はご多分に漏れずラットやノネコ、ノブタが在来種の動植物に甚大な被害をもたらしています(ただし、2種いるラットのうちナンヨウネズミはヨーロッパ人ではなく、ポリネシア人の分散に伴って侵入したものです)。その一方で、鑑賞や養蜂などの目的で導入されたカエンボク(図3)やアカシアといったマメ科の木本や、もちろんシカなど、資源として活用されている移入種も多く存在します。どこにでも生えている移入種のキイチゴが、人間だけでなく、在来のメジロ類の大好物というのは象徴的といえるでしょう。つまり、種子散布者としてキイチゴの分布拡大の手助けをしているのはほかでもない在来メジロであり、認めがたいけれど、多くの移入種はもう既にニューカレドニアの生態系の一部になってしまっているというわけです。

ニューカレドニアはゴンドワナ大陸の残存陸地であり、その稀有な生物多様性は、歴史の古さと、超苦鉄質と呼ばれる重金属を多く含んだ土壌で生き物たちが特殊な適応を遂げてきた結果、もたらされたものと考えられています。鉱物資源利用の歴史は古く、20世紀初頭には日本からも多くの方がニッケル鉱山労働者として移民したそうです。そして、そのような大規模な鉱山開発の結果、地球上でたった1本の木しか残っていない樹種が存在しているなど、絶滅危惧種の宝庫にもなってしまっています。ユーカリと同じフトモモ科で、tea treeとして知られているニューカレドニア原産のニアウリ(図4)が、島の外に出ればかなり質の悪い侵入種になっているのは皮肉としか言いようがありません。ニッケルを始めとするレアメタルはIT技術に不可欠であり、家電からハイブリッドカー、我々が喜んで使っているスマホやタブレットだけでなく、個体数推定をするためのパソコンなど、ハイテク機器が安価で手に入る社会も、こうした希少種・絶滅危惧種の累々とした屍の上に成り立っていることを考えると、つい悩んでしまいます。
シカ肉は確かにおいしいですが、地球上のどこで食べても、複雑に絡み合っていて解決の糸口が見えない生物問題の味でもありますね。我々ができることといえば、シカ肉をたらふく食って活力に換え、こうした問題に立ち向かっていくことぐらいでしょうか。

| No.132 | 一覧に戻る | No.131 拾う、残す、利用… |