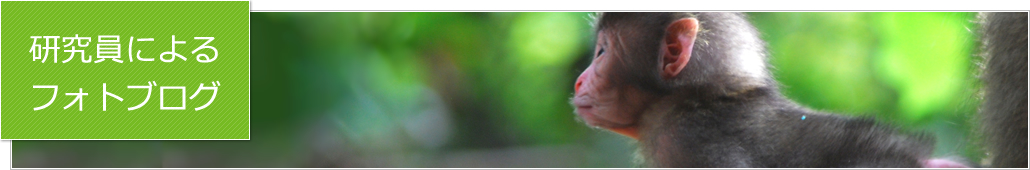No.474 電線の記憶「碍子(がいし)」
2025年08月15日
海田明裕
調査後、今は使う人もいないであろうただの窪みとなった古い山道を下山していると、道沿いの木の幹の低いところに点々と白いものが続いているのが見えました。
キノコにしては等間隔すぎる。
だんだんと近寄っていくとそれは碍子(がいし)であることがわかりました。
碍子とは磁器でできた筒状のもので、周囲に溝が一周しています。
電線を支柱に懸架する時に使われる部品で、支えるものとの絶縁を保つ役割があります。
碍子に電線を引っ掛けはするけれど磁器なので電気は支柱側には流れないわけです。
ただ、この碍子達は電柱に固定されているのではなく、生えている木に直接打ち込んで使われるタイプのようです。
こういったタイプの碍子は初めて目にしました。
まあ、たしかに山の中にいちいち電柱を立てるよりはもう立っている木を使うほうが楽に決まっています。
現代では見つかったらかなり批判されそうな方法でありますが、これはもう設置されてから数十年は経過していそうです。
ほとんどのものはまだ木の幹の表面から突き出ていて、やろうと思えばまだ碍子として役割を果たせそうな状態でしたが、一部のものは木の幹に取り込まれ始めていました。
完全に飲み込まれるまであと十年というところでしょうか?
打ち込まれた方もただ黙っちゃーいないという感じに思えました。
この電線がどことどこを繋いでいたかはわかりませんでしたが、碍子を人力でコツコツ打ち込んでは巻かれた重い電線を引き引き設置した先人達を想像しました。
はじめに見たときは、膝丈くらいのえらく低いところに設置してあるので間違って触ったら危ないじゃないかと思いましたが、私が設置するならやはり高いところに何百個もは面倒でやってられないな、と思い直したのでした。
| No.475 スダジイ界の玉井… | 一覧に戻る | No.473 福島事業所は城だ… |