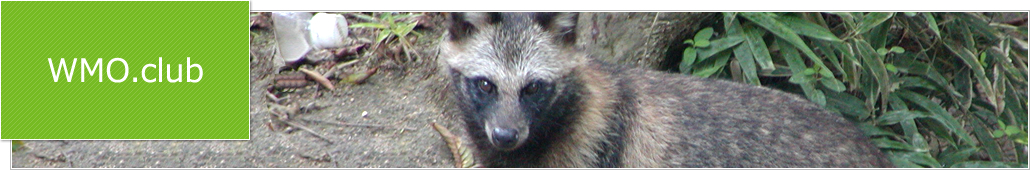No.97ネズミに思いをはせよう!
ネズミに思いをはせよう! 山元 得江(WMO) 明けましておめでとうございます。今年は「子年」ですね。年男、年女の方もいらっしゃると思います。ネズミは私たちの生活に密着しているものから、あまり関与しないものまで幅広く存在します。ネズミが人間にとって身近な存在であったのは昔からのようで、このことは古来より伝わる言い伝えや風習、諺など様々な分野でネズミが登場することからも伺えます。一方で、私たちが普段は目にできないネズミ、森林棲の野ネズミの生態はまだまだ解明されていないことがたくさんあります。今回は、今年の十二支であ…
No.97
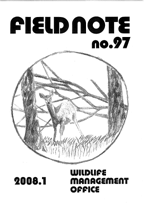
・25年目のご挨拶
・ネズミに思いをはせよう!
・アライグマのねぐら
・下北の国から’07
・映画「OUR DAILY BREAD いのちの食べ方」を見て
・糞塊密度調査の楽しみ(1)
・WMO活動報告 2007年10月-12月
No.96 NZの空港検疫を体験して
NEW ZEALANDの空港検疫を体験して 佐伯 真美(WMO) 入社前の話になりますが、昨年3月にニュージーランドに行きました。今回はその時、体験したニュージーランド(以下、NZ)の空港検疫について書かせていただこうと思います。 NZという国名を聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか?先住民のマオリ族?飛べない鳥のキウィ?NZの国技であるラグビー?映画「ラストサムライ」や「ロード・オブ・ザ・リング」などの撮影地?世界一の散歩道と言われるミルフォード・トラック? 私がNZに行きたい!と思った理由の1つは、NZの…
No.96
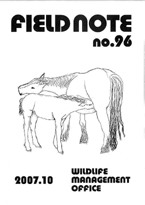
・サルの道草民俗学-サルにまつわる現代の逸話-
・富士山北麓地域のニホンジカの季節移動、生息地利用及び林業被害
・NEW ZEALANDの空港検疫を体験して
・第13回日本野生動物医学会 岩手大会 参加報告
・日本哺乳類学会2007年度大会 参加報告
・WMO活動報告 2007年7月-9月
No.95 カワウを訪ねて竹生島 (加藤 洋)
カワウを訪ねて竹生島 加藤 洋(WMO) かつて「深緑 竹生島の沈影」といわれた島。 滋賀県琵琶湖、ここにはカワウによって大きく変化していく島がある。 竹生島は、琵琶湖の北部に位置する周囲2km、面積0.14km2の島である。全島が花崗岩の一枚岩からなり、標高197.6mの急峻な地形をしている。この島には、歴史ある建物がいくつもある。島の斜面、勾配の急な165段の石階段の上に建造された宝厳寺は、神亀元年(724年)、聖武天皇により使わされた僧・行基により建立されたと言われる。都久夫須麻(つくぶすま)神…
No.95
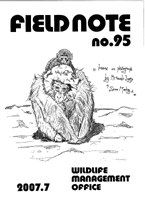
・カワウを訪ねて竹生島
・ナウシカの憂鬱、人類の優越
・カバの壁
・畑しごと
・兵庫県森林動物研究センター シンポジウム
-りぶ・らぶ・あにまるず シンポジウム2007-
『シカとイノシシの有効活用』参加報告
・WMO活動報告 2007年4月-6月
・お知らせ
No.94 2006年クマ大量出没が語るもの
2006年クマ大量出没が語るもの 片山 敦司(WMO) 2007年2月9日~11日、日本クマネットワーク(JBN)が主催する「緊急クマワークショップ」と「緊急クマシンポジウム」が東京で開催された。前者はJBN会員と行政担当者など、クマ問題の前線で格闘している人々が、2006年度のクマ大量出没の原因、対策、課題等を総括し、今後のクマ類の保護管理の方向性をJBNからの提言という形でまとめあげるというもの。後者は、一般向けのシンポジウムで、「人里に出没したクマをどうするのか?・人里に出没させないための方策は?-2006…
No.94
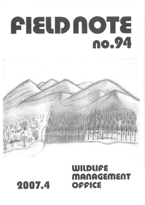
・鳥獣保護事業計画の基本指針と地方環境事務所の強化
・2006年クマ大量出没が語るもの
・アライグマ五年生の勉強ノート
・タイワンジカの運命
・新人紹介
・WMO活動報告 2007年1月-3月
・お知らせ
No.93 イノシシの牙
イノシシの牙 岸本 真弓(WMO) 今年はイノシシ年。 いろいろなイノシシの年賀状をいただいた。かわいいイノシシ、リアルなイノシシ、勇ましいイノシシ。ブタとの違いは粗い毛と、鋭くむいた牙のようだ。それが一般の人が抱くイノシシの姿なんだろう。 だが、実際にはイノシシの牙はオスの成獣でしか目立たない(写真1,2)。それにサイの角のように前に突き出ているのではなく、後ろに湾曲している。正確に言うと、前に弧を描くように湾曲し、先端は斜め後ろを向いている。これは下の犬歯で、不思議なのは上の犬歯も同じようにカーブしていることだ…
No.93

・2007年・年始のご挨拶
・イノシシの牙
・ミャンマーに生息するサル(マカク類)捕獲調査報告
・「ヒバの宿」
・アフリカ旅行記
・WMO活動報告 2006年10月-12月
No.92 秋の山、クマの暮らしを垣間みた
秋の山、クマの暮らしを垣間みた 瀧井 暁子(WMO) フィールドノートの原稿の締切りがとうに過ぎてしまった(編集者さん、ごめんなさい)。その頃、私はY県境付近の山の中でシカの糞塊調査を行っていた。 この調査は、単独で山の尾根を5~6km歩きながらシカの糞を記録するものである。登山道もあれば、道のまったくない尾根もある。調査範囲は、標高約900~2000mであり、スギ・ヒノキ・カラマツなどの植林地のほか、標高1600m付近まではブナ・ミズナラ林が多く、標高1600m以上は、主にコメツガ林となっている。…
No.92
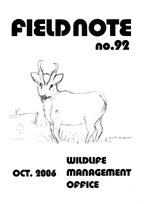
・ケニア滞在記
・秋の山、クマの暮らしを垣間みた
・霊長類学会に参加して
・日本哺乳類学会2006年度大会参加報告
・図書紹介「タンポポ タヌキ、もりのタネ。」
・WMO活動報告 2006年7月-9月
No.91
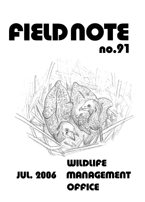
・リセット
・仕事は野生を守ること
・六甲山復興の歴史
・アライグマ四年生の勉強ノート
・セネガル旅日記
・うんこのだし方、いかし方
・第17回国際クマ会議(IBA2006 Japan)開催迫る
・新人紹介
・WMO活動報告 2006年4月~6月
No.91 うんこのだし方、いかし方
うんこのだし方、いかし方 岸本 真弓(WMO) 昨年秋、例年通り訪れたのシカ糞塊密度調査対象地である福井県、兵庫県、滋賀県の山の実りは見事だった。標高の高いところでは、ブナ拾いに熱中した。しぶみやえぐみをとことん敬遠しているはずのヒトでさえ、おいしいと感じるブナの実を、山の動物たちが大好きなのは当たり前、私なんぞに拾われては怒るだろうなと、ちょっとビクビクしながら拾い集めた。一緒に調査に行ったY山さんは、果樹園状態のアケビを発見。私もおすそわけにあずかった。このおすそわけにヒトは舌鼓を打ったわけだが、タヌキは山の実…
No.90 続・仙台のニホンザル
続・仙台のニホンザル 清野 紘典(WMO) 2006年3月10日・11日、京都大学霊長類研究所において共同利用研究会「野生霊長類の保全生物学」と題した研究会が開催されました。学生時代に共同利用研究にお世話になっていたこともあり、研究発表を行いました。 発表の内容は、仙台市に生息する野生ニホンザル群の生態についてでしたが、今回そのすべてを紹介するには限りがありますので、『Field Note No.75』で森光(WMO)によって報告されている「仙台のニホンザル」(p7-11)の続編として、仙台のサルとそれらを取り巻…
No.90
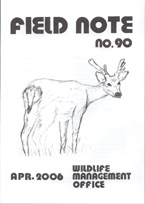
・本社移転の御報告
・続・仙台のニホンザル
・アメリカ研修報告
・新人紹介
・WMO活動報告2005年10月~12月
No.89 『人慣れグマ』との正しい「付き合いかた」とは?
『人慣れグマ』との正しい「付き合いかた」とは? ―クマの夏2005― 泉山 茂之(WMO) 毎年、夏は休む間もなくクマと向き合う日々が続く。北アルプス南部の上高地周辺では、ホテルや山小屋でのゴミ管理が行き届くようになり、生ゴミに餌付いて問題を起こすクマはほとんどいなくなった。 ところが、2002年頃から、遊歩道の周辺で日中からふらふら徘徊する仔グマが話題になり始めた。親グマから離れて間もない仔グマが連日目撃され、観光客からは携帯シャッターの嵐で、人気の的だったそうだ。 確かに、仔グマはかわいいかも知れない。このよう…
No.89
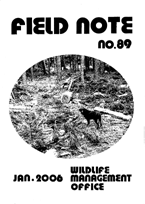
・熊のタナが消えた
・『人慣れグマ』との正しい「付き合いかた」とは?-クマの夏2005-
・アカシアの樹の下で
・足澤さんの訃報に接して
・足澤貞成さんをしのんで
・「心の進化を研究したいんだ」追悼足澤貞成さん
・足澤さんとの思い出
・「酒を愛せ・・・・・」
・カリブ-と出会ったアラスカの旅
WMO活動報告2005年10月~12月 / 図書紹介
No.88

・下北にて(9)
・ミバエ撲滅キャンペーンに学ぶ外来種対策
・庭のカマキリをみて生物多様性を感じる
・IMC9参加報告
・第9回国際哺乳類学会(IMC-9)参加報告
タヌキのため糞調査結果を発表しました
・日本霊長類学会大会参加報告
・ヒガンバナは不吉な花なんだろうか・・・
WMO活動報告2005年7月~9月 / お知らせ
No.88 ヒガンバナは不吉な花なんだろうか・・・・
ヒガンバナは不吉な花なんだろうか・・・・ 横山 典子(WMO) 暑さ、寒さも彼岸までといわれますが、すっかり涼しくなり、秋らしくなってきました。 先日、どこかに出かける途中でヒガンバナを見ました。黄金色に輝く田んぼを赤く縁取っているかのようにヒガンバナが群生している風景に、日本人の色使いのセンスの良さに感じ入り、本当に日本って美しい国なんだとガラにもなくしみじみとした気持ちでしばらく眺めていました。その時に、昔読んだ本の中にヒガンバナは自生しているのではなく、植えられたもので、田んぼの畦にモグラやネズミの侵入を…