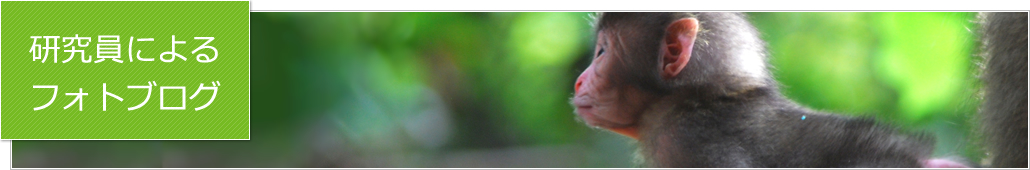No.444 フランスパンは硬くて好き

海老原寛 あー、山登ってきて疲れたな。 そろそろお昼だし、ちょっと休憩するか。 どっこいしょ。 今日はお昼ごはんに何買ったんだっけな? あぁ、そうだソーセージ入りフランスパン買ったんだった。 さぁ、食べよう。 いただきま・・・・あれ? 同じの2つも買ったっけな?
No.443 隠しご飯見つけた!

海田明裕 足を止め、進むべき方向の地形を確認しようと目線を上げたとき 斜め前にボロボロの枯木が立っていました。 穴だらけの幹の中に艶のあるものがチラリと見えた気がしてよく見ると 狭い空間にどんぐりが1つだけ挟まっていました。 上から落ちたものかと思いましたが、見上げた視界の中にはどんぐりをならす木は見当たりません。 隙間の狭さから想像するに、ネズミよりもカケスなどの鳥の仕業ではないかと思われましたが確信はありません。 隠し主がだれかは置いておいて、なんとなく他人の秘密を見てしまったような気持ちになりました。 このど…
No.442 BIGエビフライ!

中島彩季 “森のエビフライ”と呼ばれるだけあって、松ぼっくりのリスやムササビなどの食痕は見事にエビフライに似ている。 ある時とても大きなエビフライを発見! リスたちは一度に1個食べきれるのだろうか、なかなかなボリュームに思える。 正体はテーダマツだった。 テーダマツよりも大きいゴヨウマツの食痕もエビフライ状になるのか?そうなるともっと大きなエビフライが存在する?? 新たな疑問(期待)が生まれた。 ゴヨウマツが生えている場所で調査する機会があれば探してみようと思う。 (・・・ちなみに、テーダマツの“エビフライ”は、そ…
No.441 ツッコミ待ち

海老原寛 琵琶湖には、釣り上げたブラックバスなどの外来魚を放流してはいけない条例があり、外来魚回収ボックスや回収いけすが多く設置されている。 ん? お前、立場わかってんのかい! (ヌートリアは、外来種です) 実際には、ボックスの中に在来魚やヌートリアの死体が入れられてしまっていることもあるらしいです。 外来種駆除も必要ですが、ルールは守ってほしいですね。
No.440 燃える山、燃える尻

森洋佑 シカを探しに山梨県の山に行ってきました。 ちょうど紅葉の盛りで、山全体が燃えるように真っ赤になっていました。 とても綺麗でシカを探しつつ、山の景色も撮りつつの踏査でした。 調査地の紅葉 調査地の紅葉 燃える山 期間中、天気も良く調査日和が続きました。 シカの痕跡も多く、シカを見つけるのも時間の問題だと思っていたのですが。。。 なんと調査終了日が近づいても一向にシカに出会えません。 これはヤバい!もしかしたら本当に燃えているのは山ではなく私のお尻!?
No.439 天然大砲

姜 調査中の山中で写真のように、倒れた木(写真1)のその形状(写真2)や先端が空洞(写真3)になっているのを見た瞬間、大砲を連想しました。 ウクライナとロシアの悲惨な戦争が続いており、世界にますます不安を与えていて、とても心配です。一刻も早く戦争が終結し、全ての人が普通の日常に戻れるように祈るばかりです。 妄想ですが、もし本当に神様がいるのなら、人類の普遍的な価値を守りたい側に、強力なこの天然砲を与えて勝利の決着をつけられるように助けてあげてほしいと切に願いました。
No.438 よく見ると顔はかわいい(と思う)

海老原寛 8月のある日、家の窓の桟にたくさんフンが付いているのに気付いた。 何かの虫かな?とも思ったが、特に餌となる植物があるわけではない。 これは・・・と思い、通気口をのぞいてみると、やっぱりコウモリがいました。 一度気付くと気になるもので、それから定期的にのぞいていました。 いる日といない日がありましたが、だんだん見かけることが少なくなりました。 どこか行ってしまったなぁと思っていた、10月のある日ベランダを見ると、見覚えのあるフンが。 給湯器の真下にあるという不自然さはありましたが、今度こそハトかな?と思いつ…
No.437 意外な犯人
平山寛之 私の自宅ではこのところ事件が続いている。ブロックの上に茶色いゴミのようなものが散乱した状態になっているのです。 集めたのがこれ。 茶色いゴミのようなもの、すべてミノムシです。しかも、中身は空でミノのみ。片付けても片付けても翌日には元通り。2週間ほど続いていました。 ミノムシが一斉に羽化するようなことはないだろうし、不思議だなと思っていました。毎日の片付けに疑問がなくなるほど続いたところで、解決編。 早朝に訪れた2羽のシジュウカラが器用にミノムシをほじくり出して食べる。その時の止まり場が先のブロックでした。…
No.436 尾瀬の春の異変

姜 2013年に調査の為に尾瀬ヶ原を訪れ始めてから11年が経つ中で、今回初めてゴールデンウイークに訪れました。5月3日にもかかわらず尾瀬ヶ原の湿原にはほとんど雪が残っておらず(写真1、2)、今までに無く雪解けが早いことに驚きました。 尾瀬を訪れた他の人々は、この時期に水芭蕉(写真3)を見ることができ嬉しかったと思いますが、私はこのような早い時期に水芭蕉を見られたことに、とても不安を感じました。 雪解けが異常に早いのは、各年の気象条件の違い(例えば冬季の積雪量など)によるものもあるかもしれませんが、私自身、11年前か…
No.435 心躍る瞬間

中島彩季 シカの糞塊密度調査中に見つけたもの。 ルート上に落ちていたシカ糞を良ーく見ると、イガグリの棘に刺さっていた。 ちょっと心が躍った。 イガグリの棘は地面に手をついた時に手に刺さることがあるが、非常に痛い。 シカ糞が刺さっている様子を見て、改めてその鋭利さを実感した。 山を歩いていると、こうした面白いものを発見することが度々ある。 野外調査の楽しみのひとつである。
No.434 恐竜の卵化石ではなかった!

先日、No.412で「恐竜の卵化石を発見!」を報告したが、恐竜化石の専門家に確認してもらったところ、残念な結果となってしまった。その主たる根拠は、卵の「殻」に見える部分の厚さが一定ではない事(写真1、2、No.412の写真も参照)であった。恐竜の卵化石の殻の厚さは、肉眼では僅かな違いを見分けるのが困難な程、どこを取っても大きく変わらないそうだ。 この正体は岩石が玉ねぎの薄皮のようにはがれる、「風化」の一種であった。岩石の表面と岩石内部の膨張量の差による歪みによって、割れ目が生じる。さらに岩石に染み込んだ水や日光によ…
No.433 尾瀬での休日

WMOでは尾瀬ヶ原や尾瀬沼でも仕事をしています。 繁忙期には数週間にわたって尾瀬に泊まり込むことも珍しくありません。 そんな折、週末の2日間だけ東京に帰る代わりに、現地でお休みをもらうことにしました。 天気も良かったので東北地方最高峰の燧ヶ岳に登ってきました。 仕事で歩き回る尾瀬ヶ原も尾瀬沼も一望でした。「あの林、林床はササばかりで歩くの大変なんだよな・・・」「あそこはシカ見たところだ」とか思いつつも、最後は「やっぱり綺麗だ・・・」と見とれてしまいます。 燧ヶ岳 燧ヶ岳から見た尾瀬沼 &…
No.432 誘拐犯に注意

岸本真弓 調査中ではないです。朝、出勤前に自宅の前の道を歩いていたらかわいいコシアカツバメがうずくまっていました(写真1)。手が触れそうなくらい近づいても動きません。よく見ると産毛がまだあって、どうやら巣立ちビナのようです。 こんなところにいたら急ぎ足の人に踏まれるか、保護という名の誘拐にあってしまうよ。 鞄でチョイチョイっとおっ立てて生け垣の方に寄せてあげました。あとはお母さんにお任せです(写真2)。 写真1 写真2
No.431 都庁登庁?

森洋佑 フォトブログを見ていると、WMOの職員はみんな山ばかりに行っているように思えてしまいますね。実は山だけでなく都会へ行くこともあるのです。 写真は書類を届けに新宿の都庁に行ったとき、お使いが早く終わったので最上階の展望室に行って撮りました。 都心の街並みから富士山まで一望することができました。 都庁展望室からの眺め 丹沢山地や関東山地の後ろに富士山が見える。 真下を見てみました。公園に都庁の影が映っていました。
No.430 高嶺の首輪

ペンネーム:ユージ 先日の宮城県でのクマの首輪探索中 ずっと近くで探索音がしてるのに見つからない、、、 当たりの地面をイノシシのように、落ち葉をかき分け探しまくり、諦めかけたところ 再度アンテナを振ってみると、上の方が強いような気がー (⇩この中にあります!) 正解は写真中央付近。そんなとこにどうして、、、 同じブナの木にはクマの登った跡が! モグモグとブナの実を採食中に木の上で外れてしまったのか。僕がクマなら相当ビビる、、、
No.429 気まぐれな木

ペンネーム:たぬぞう 調査の帰りに変わった形の木を見つけました。 なぜ彼が(彼女か?)こうなったのか、まったく見当つきませんが、私はなんだか「絶対生き延びてやる!」という不屈の精神を感じた気がしました。 とまあ、自然の中にあるいろいろな不思議に出会う度に、なんでこうなったのだろうなんて妄想して楽しむのですが、むしろ不思議に見えているのは自分だけで、これは当たり前の姿だったりするのかなとも思います。いつだって自分が見えているものは、自分のフィルターを通してしか見ていないのだと、たまに立ち止まって思い出すようにはしてい…
No.428 丹沢山の怪物?

森洋佑 みなさんは「ブロッケン山の怪物」を知っていますか? 山を登っていると霞の中に怪物が現れるという現象です。 手塚治虫の漫画『ブッダ』ではサーリプッタとモッガラーナが弟子を説く場面で登場します。そこでは怪物ではなく、畏敬の存在として描かれます。 先日、丹沢山でシカを追いかけているときにそんな現象に出会いました。ブロッケン現象は、ときどき見ることはあっても、自分の腕を動かしたら霞の中の私も動くくらいはっきり見えたのは初めてでした。 さて、このブロッケン現象、みなさんは怪物だと思いますか、それとも畏敬の念を抱きます…
No.427 ホールインワン、下から上へ

海田明裕 フォトブログNo.384 、398でふれられた、森の中のホールインワンですが、今回は下からのホールインワンです。 比較的地面ばかりみて歩く種類の調査中。あまり使われなくなった登山道がササに覆われかけているような場所を歩いていました。 視界のほとんどが緑色ばかりのなかで、茶色が目につきます。 はじめはなにかキノコの類かと思いましたが、どうも薄っぺらい。 近づくと、それは虫食い穴をササに貫かれ、宙に持ち上げられた落ち葉でした。 死ぬほど落ちている落ち葉と、そこいらじゅうに生え出てくるササの芽であろうから、そん…
No.426 春きたる2

森洋佑 「そろそろかな」と思いながら見てきました。春、来ていました。 私の通勤経路に片倉城址公園があります。そこは知る人ぞ知るヤマブキソウのお花畑があるところです。「そろそろかな」と思いつつ、30分ほど早く家を出て寄り道してみました。 春、来ていました。見とれてしまうくらいきれいでした。 満開のヤマブキソウ 片倉城址公園はヤマブキソウだけでなく多くの花が咲くところです。カタクリはもう花期が終わって果実になっていましたが、イチリンソウやニリンソウはちょうど良い時期です。緑色の花で目立たないですがナツトウダイも咲いてい…
No.425 春きたる1

森洋佑 年度末が終わり、3月下旬から4月上旬は少し余裕のある時期です。お昼の時間にもうちょっと遠くまで足を伸ばすこともできます。 この日も陽気に誘われて歩いていたら、本社裏手の土手のソメイヨシノがとてもきれいに咲いていました。土手には胞子を出し終わったツクシも。 サクラは今が大忙し、ツクシは私と同じく一仕事終えた感じでしょうか。 土手の上のソメイヨシノ 土手のツクシ